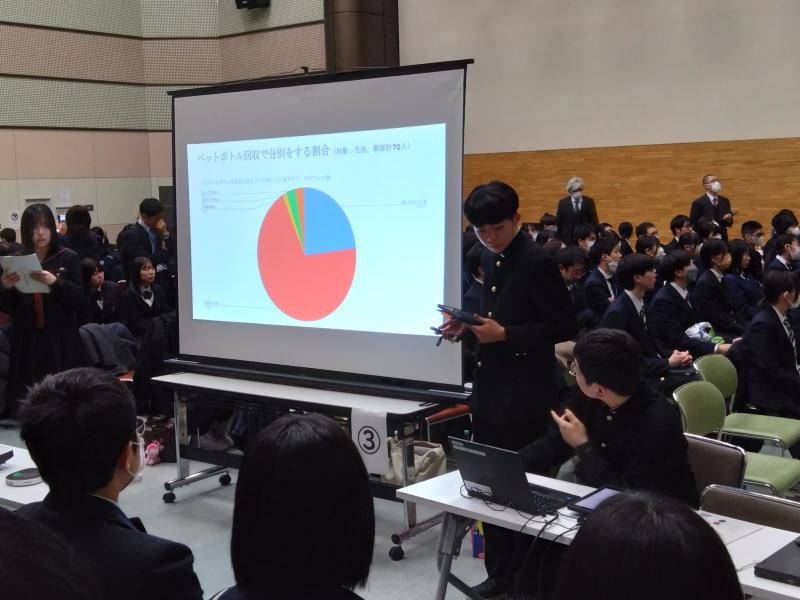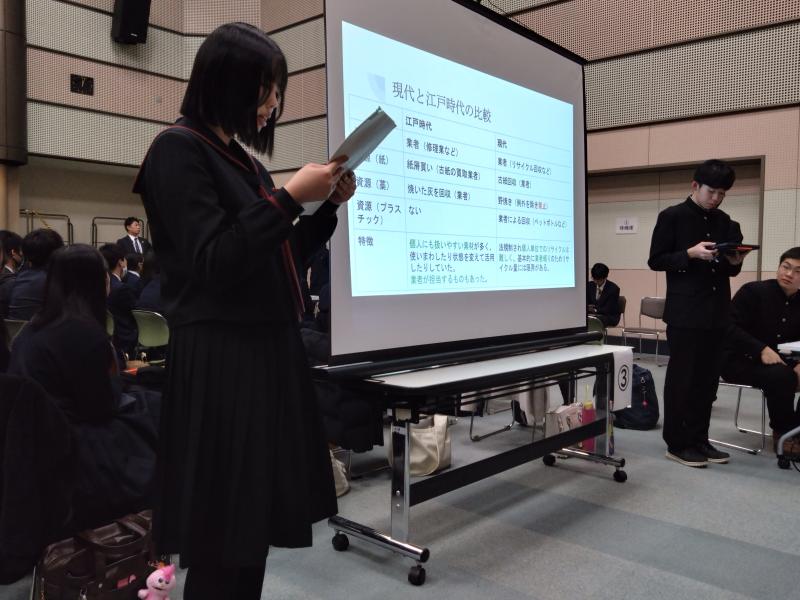力行タイムブログ(全日制進路指導・探究キャリア支援部)
令和7年度 探究基礎講座③「データサイエンス講演会」
令和7年5月30日(金)1~2時間目に、秋田大学情報データ科学部教授 有川 正俊 氏をお招きして、「データサイエンス(DS)をなぜ学ぶのか?」というテーマで、効果的な情報の集め方と分析の仕方を学びました。
【生徒感想抜粋】
・データサイエンスを利用して、未来の課題を見つけたり、自分自身の発展に繋げれたりするのではないか。また、ゲームにもデータサイエンスが利用されていて、
更に知りたくなった。
・データとは、存在するさまざまな情報をかき集めて活用し、分析して作っているとわかった。さらに、データやAIを利用することによって日常生活の中でも、
データに触れることができる。
・アプリなどの話を聞いて青森県の観光地をガイドするアプリを作れば、多くの人を呼べることができるかもと思った。
・データ収集から得られる知識をもとに、仮説を立ててそれをまた研究することで、新しい気づきや発展につなげることができることを知った。そのため色々な
ことに興味を持って、探究心を持つ大切さを学んだ。
・AIに支配される世界ではなく人間がAIを支配する世界であると知り驚いた。
・データを扱うことによって、今の日本の課題や現状を変えることのできる手掛かりになったりすることがわかった。
・より良い生活を送る為には日本国民一人一人がネットワークの利便性と危険性を理解・意識し、更なる充実した生活・利益の追求・環境の保全の為に、そして
これからの未来を生きる人たちの為に考え続けなければならないと思った。
・ただ口頭や文章で説明されるよりも、データやデータの移り変わりを提示されると説得力があって聞きやすいと感じた。
・大規模なデータを活用することで今私たちが使っているアプリなどが使えているというありがたみを改めて感じた。データはこれまでの記録だけではなくこれ
から先の未来を見据えることができるので、これから先日本だけではなく、世界規模で今まで以上にいろんなことが進歩していくと思う。そんなこれからの未来
を生きていく私たちがもっともっと先の未来を考える必要があるなと実感した。
令和7年度 探究基礎講座③「プレゼンテーション講座」
令和7年5月21日(水)6~7時間目に1学年生徒を対象に「プレゼンテーション講座」を行いました。書家・プレゼンテーションクリエイター・一般社団法人 継未(TUGUMI)代表理事を務めている前田 鎌利氏に、「自分の意見を論理的に構築し、相手に伝わる話し方を学ぶ」ことについて、お話していただきました。







【生徒感想抜粋】
・プレゼンに対する意識が変わった。講演前前はただ伝えるだけだと思っていたが、自分の言葉で相手に納得させて動かすことだとわかった。
・自分という個人としての考えの大切さとそれをしっかりと伝える事とはどんなことかを学ぶ事ができた。
・「迷ったらやる」が心に響きました。
・プレゼンは自分の考えを理解しやすいように目に見える形で表すもので発表とは違うことが分かった。相手にしっかり伝えられるテクニックが
たくさんあって、これまでの間違いなども見つけることができた。
・プレゼンの仕方よりも大切なことを学ぶことができた。誰が見ても凄いと感じさせる人は経験だけでなく、経験を無駄にしない努力を積み重ねる。
・プレゼンは人を動かすことができるもので、相手に情報だけでなく、勇気や希望を与えられるように作ることがポイントとしてとても大切だ。
・海外に行っていたり自分で図書館を立ち上げていたりとさまざまな経験をされてきたからこそこんなに説得力があると思った。今日の質疑応答で
勇気が出なくて質問できなかったが、これから小さいことから少しずつ挑戦して人前で話すことの苦手意識が少しでも減ればいい。
・人に注目を自分に向けさせる方法や、上手いプレゼンを作るにはプレゼンの設計図が必要なことなど、今度重要になるプレゼンの作成の仕方に
ついて、とても参考になった。上手に伝えるメカニズムなどを学ぶことができ、とても有意義な時間を過ごせて講師の方にとても感謝している。
・1番印象に残っているのは、一万時間の法則です。何にでも一万時間すればプロになれるので、自分に足りないところはとことん時間をかけて
克服し、部活でも何回も何回も練習してプロに近づけるようになりたい。
令和7年度 地域探究・探究基礎講座②「立佞武多講演会」
5月8日(木)午後、株式会社パークイン五所川原代表取締役社長 中山 佳氏をお招きして、「立佞武多と地域経済、そして未来の可能性」という題で講演をして頂きました。その後、①「五所川原市の地域経済がより発展するには何が必要か」②「立佞武多の館に代わる観光コンテンツ」③「今後どのような形で立佞武多(五所川原市)と関わっていきたいか」について、テーマを選んでグループで話し合いました。
| 学んだこと |
・まだ歴史が浅く2023年に運行開始から25周年をむかえた。 ・市全体で関わり合いながら五所川原立佞武多としての青森ねぶたとは違った魅力を確立している。 ・今まではやることが普通だと思ってたけど、多くの人の努力で今やっているというのを聞いてすごいと思った。 ・高さ20メートルを超える立佞武多の迫力には圧倒され、その精巧な造形や彩色が、いかに多くの時間と技術、そして情熱によって作られているかがよくわかった。 ・立佞武多の祭りが開かれたことによる経済効果は30億円と思ったよりも多くてびっくりしたと同時に、それだけの効果があるお祭りはもっと多くの人に知ってもらうべきだし、それで地域を盛り上げたいと思った。 ・祭りを見るために五所川原に滞在したい観光客は多いのに、市内にはホテルが3つしかなく、不足していることも初めて知った。 |
| 今後の対策 |
・なにか良い案を出しても、費用面で困難なことが多くあるなと思った。 ・立佞武多の模型を販売したり、ランダムで歴代の立佞武多のデザインをしたマスコットなどを販売するなどは手に取りやすくて面白くて良い。 ・地域で運行するねぶただけでなく、観光客が実際に体験することができる機会を与えてみる。特に外国の人たちに参加してもらうことで、自分の国などに帰省した際に自慢したくなるような機会を与えて海外にもさらに発信できたらいい。 ・私たちも地域の伝統やかけがえのない財産を次の世代に渡すために今何をすれば良いのかを真剣に考える。 |
| 感想 |
・雪でたちねぶたを作るというのが面白かった。 ・伝統を守ることの大変さと、それを支える地域のつながりの大切さについて、これまで以上に深く考えるきっかけになった。 ・立佞武多の館が休業している間、どうするのかと思っていたのでこの機会に色々な話を聞けて良い機会になった。 ・五所川原では現在自然減、社会減という人口減少が問題になっている。今総探で似たような課題に取り組んでいるので良い機会になった。 |
令和7年度 探究基礎講座①「五所川原市の現状と課題を知る」
4月24日(木)午後、五所川原青年会議所から島谷 昌孝氏をお招きして、「『奥津軽虫と火まつり』の現状と課題について」という題で講演をしていただきました。
【生徒感想抜粋】
| 課題 | 少子高齢化やコロナ禍の影響で祭りの認知度が下がっている。そのためこれまでできたことが金銭面でできないことがある。 |
| 課題 | いろいろな点で経費削減に努力しているので、資金を集める場を増やす。 |
| 課題 | 安全に配慮しながら伝統を守っていく。 |
| 学んだこと | 過疎化が進んでいるからこそ、小中高の生徒たちが協力することが大事だと学んだ。 |
| 学んだこと | 地域を盛り上げるためには、行政に頼るのではなく、私たちが主体的に行動することが大切だ。 |
総合的な探究の時間「進路探究」(0829)
総合的な探究の時間「先輩から学ぶ」(0531)
地域探究「地域課題を探る」
地域探究「伝統文化の継承①」
あおもり創造学「成果発表会」(2月7日)に参加してきました。
(作成中)